こんにちは、パンチです。
最近ふと思ったんですよ。
「なんか“読書家”って名乗るの、ちょっと勇気いるな」って。
特にさ、「純文学は?」って聞かれたときのあの空気。
ラノベやビジネス書ばっかり読んでると、「あ、そっち系か…」みたいな視線を感じるとき、ないですか?
いやいや、読書って自由じゃなかったっけ?
というわけで今回は、「純文学を読まないと読書家じゃないの?」っていう、ちょっとめんどくさい話をゆるっと語ります。
そもそも純文学ってなんなの?
ざっくり言うと、純文学は「売れるために書かれた小説」ではなく、
「文学としての価値」を追求した作品のことです。
✔ 心の葛藤とか
✔ 人生の意味とか
✔ 社会への問いかけとか
こういった“テーマの重さ”や“内面的な描写”が重視されるのが特徴。
娯楽要素はあんまりなくて、どちらかというと「深く考えさせる系」。
いわゆる“芥川賞”とか“文學界”とかで話題になる作品がこれにあたります。
たとえば村上春樹(初期)とか、太宰治とか、吉田修一とか、綿矢りさとか、
現代なら乗代雄介、古川日出男、町屋良平あたりもこのカテゴリに入るでしょう。
で、これを読むと、「文学わかってる感」が出せる。
それが、“読書家”という看板と結びつきやすいんですよね。
読書家=純文学を読む人、って誰が決めたの?
でもさ、思いません?
「純文学を読んでないと、浅い読書」
「ラノベやビジネス書ばっかりじゃ、本を読んでるって言えない」
「漫画なんてもってのほか」
……って、誰が決めたんでしょう。
たぶんだけど、それ、「自意識」です。
世間がそう思ってる気がする。
他の読書好きがマウント取ってくる気がする。
「自分が“ちゃんと読んでる”って思いたいから、誰かより上に立ちたい」みたいな。
これ、読書好きあるあるだと思ってます。
ちょっとだけ“自分の読書はレベルが高い”と思いたい。
だから「純文学を読んでる=本物の読書家」って、どこかで自分に言い聞かせてる。
逆に、純文学を読んでないことに後ろめたさを感じてる人も、
「読書家って言っていいのかな……?」って悩んでたりして。
そのモヤモヤ、もう手放しませんか?
純文学だけが“深い本”じゃない
確かに、純文学は「深いテーマ」を扱ってることが多いです。
でも、それって純文学だけの特権じゃない。
エッセイだって、児童書だって、自己啓発書だって、
読者の人生を変えるくらいの影響力を持ってたりします。
たとえば、
- 星野源のエッセイ『そして生活はつづく』には、生きるリズムのヒントが詰まってるし、
- 東野圭吾の『ナミヤ雑貨店の奇蹟』だって、人間関係や過去との向き合い方を描いてる。
- よしながふみの『きのう何食べた?』は、食と愛情と老後を、ものすごくやさしく教えてくれる。
こういうのを「娯楽」として軽く見るのって、もったいないと思うんですよね。
「読書って何のため?」って考えたとき、
“作品のジャンル”よりも、“自分が何を感じたか”の方がずっと大事なんじゃないでしょうか。
純文学を読んでなくても、堂々と「読書家」でいいんです
「純文学を読んでないと読書家じゃない」
――そんな空気に、ぼくらは無意識に縛られてきたのかもしれません。
でも読書って、本当にもっと自由でいい。
“読むこと”そのものに価値がある。
好きな本を好きなように読む、それで十分「読書家」です。
もちろん、純文学に挑戦してみるのもアリ。
ただ、読んでないからって、自分の読書を下に見なくていいんです。
読んだ冊数でも、ジャンルでもなく、
「読書が日々の中でどう息づいてるか」が、
“読書家”かどうかを決めると思っています。
というわけで、
これからも堂々とラノベも漫画も読むし、
気が向いたら純文学もつまみます。
みんなちがって、みんな読書家。
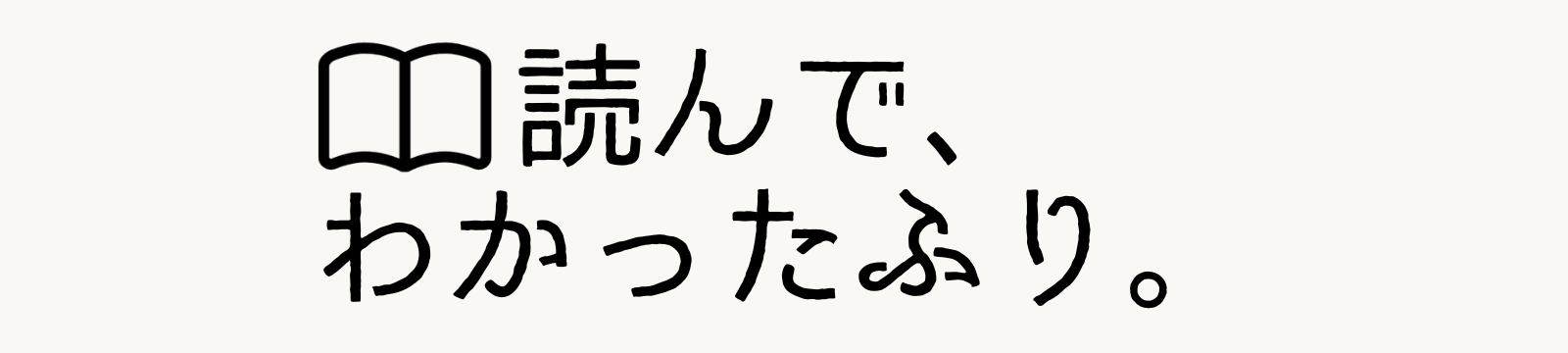
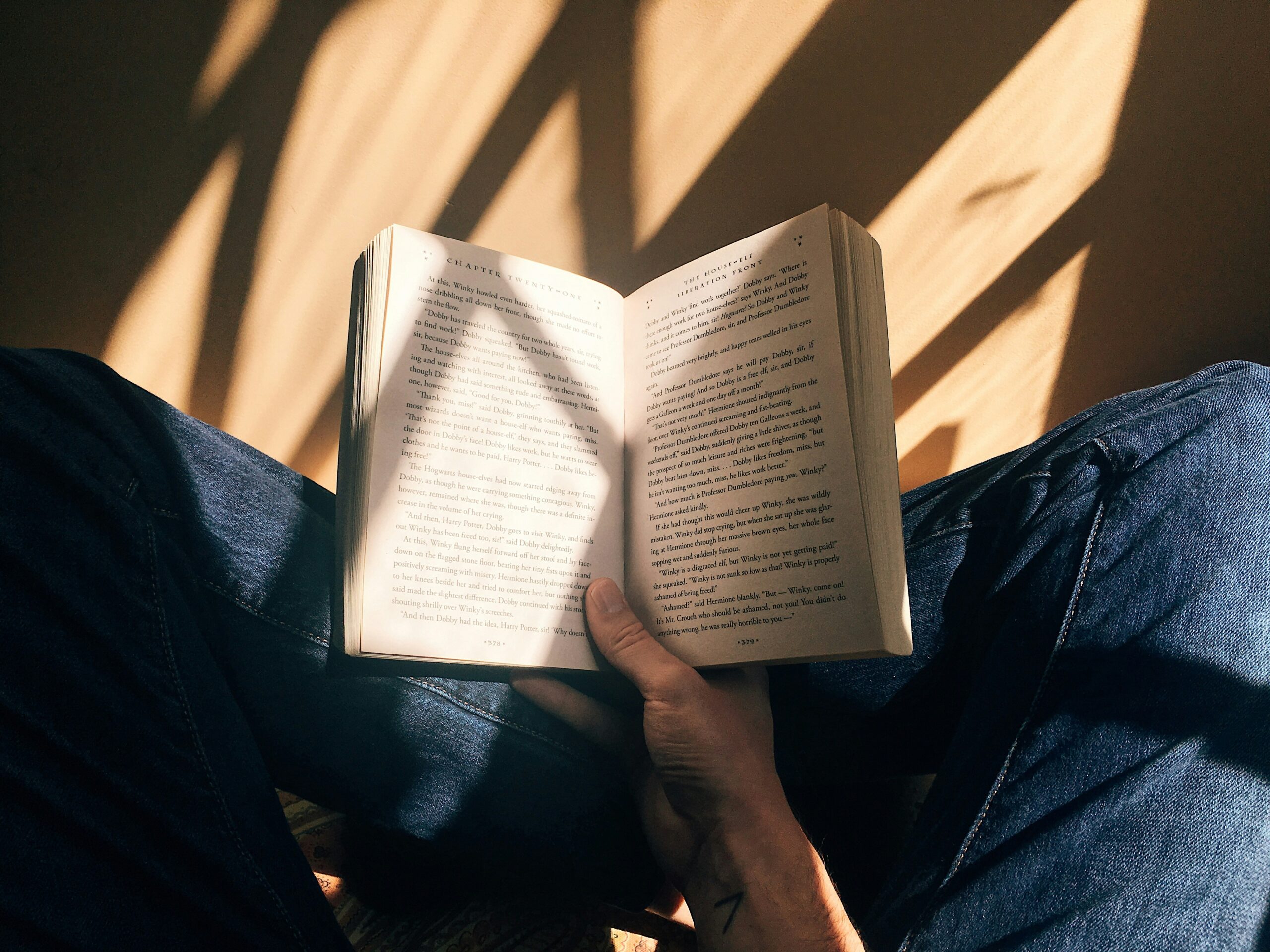

コメント