こんにちは、パンチです。
今回紹介するのは、そんな「考えすぎる人」たちに全力で寄り添ってくれる一冊。
品田遊さん(ダ・ヴィンチ・恐山)の本『納税、のち、ヘラクレスメス のべつ考える日々』です。
タイトルだけ見たら「どういうこと?税金?神様?」みたいな感じなんですが、読んでみると「あ〜これ、めちゃくちゃ“わかる”わ……」と感情が揺さぶられる不思議な本でした。
というわけで今回は、この本の注目ポイントと、おすすめポイントをじっくり紹介していきます!
目次
この本、こんな人に刺さります!
- 頭の中、いつもグルグルしてる人
- 「思考」と「日常」が切り離せないタイプの人
- 内省ってたぶん趣味かもしれない人
- エッセイが好きで、しかも“ちょっと変わった視点”にグッとくる人
- 「日記」って聞くと読みたくなっちゃう人
まずはざっくり本の紹介から
この本は、著者の品田遊さん(ダ・ヴィンチ・恐山)が、2018年から書き続けてきた日記コラムの中から厳選した文章を再編集したもの。
いわゆる「エッセイ本」なんだけど、軽く流すタイプじゃなくて、「うわ、そこ考えるの!?」ってツッコミたくなるような角度から、日常のあれこれを真面目に考えてくれてます。
しかも、毎日1500字を2000日以上書き続けてるっていうから、もうそれだけで尊敬……。
ここが気になる!注目ポイントをチェック!
毎日続ける、思考のルーティンがスゴい
まずこの本、単純に「1500字の日記を毎日続けてる」というだけでヤバい。
でもスゴいのは、それが“ただの記録”じゃなくて“思考の実験”になってるところ。
たとえば「今日はお腹が痛かった」ってだけの日も、そこから「痛みによって人はどう変わるのか」みたいな哲学に飛躍するんですよ。飛躍しすぎてもう好き。
「ヘラクレスメス」って何なの?
タイトルにある“ヘラクレスメス”。このワード、実在しません。造語です。
じゃあ何なの?って話なんですが、読んでいくと「名前のない何かに、とりあえず名前をつける」って行為自体が、けっこう大事なんだなって気づきます。
「自分でもよくわかんない感情」や「何かモヤっとする現象」って、名前をつけることでようやく正面から向き合える。
その象徴が、たぶんこの“ヘラクレスメス”なんですよね。
日常の“どうでもよさ”を救い上げる力
この本の中には「日常のどうでもいいこと」が山ほど出てきます。
でもそのどれもが、ちゃんと“考える価値があること”として扱われているんです。
たとえば「SNSで人の投稿にいいねを押すときの気まずさ」とか、「雨が降った日の気圧との付き合い方」とか。
読んでて「うわ〜〜これ、自分だけかと思ってたわ!」ってなるやつ、めちゃくちゃあります。
この本のここが最高!おすすめポイントまとめ!
① “考えすぎる人”が救われる文章
この本のいちばんの魅力は、「考えすぎる人」に対して、真正面から“それでいいんだよ”って言ってくれるところ。
世の中って、「行動あるのみ!」とか「悩む時間がムダ」みたいな風潮が強くないですか?
でも、この本はその真逆を行きます。
「悩むって、時間のムダじゃない」
「考えるって、意味のないことじゃない」
「迷うことには、迷うだけの理由がある」
そう言ってくれてるような気がして、なんかもう、ページをめくるたびに肩の力が抜けていくんですよね。
特に、寝る前にふと読み返したくなるタイプの本です。
自己否定しがちな“内向きの思考”に、ちょっとだけ光を当ててくれる。そんなやさしさが、文章のすみずみまで染みてます。
② 文体がクセになる。読みやすいのに深い!
品田さんの文章って、とにかく“読むリズム”が気持ちいいんですよ。
重たい話でも、あえてふざけたり、比喩で脱線してみたり。
「真面目に考える」ことが、ちゃんと“面白く”なるように書かれてるんです。
たとえば、「友人と一緒にいるときに、沈黙が気まずくてお茶を一気飲みしちゃう」みたいなエピソードでも、そこから「人間関係における沈黙の扱い方」まで話が飛ぶ。
かと思えば、突然「ゴリラの気持ちになって考えてみた」みたいな謎の比喩が出てきて笑わせてくれる。
その“緩急のつけ方”が抜群で、読んでて飽きない。
むしろ、読み進めるうちに「次はどんな着地になるんだろう?」ってワクワクしてくるんです。
③ 日記というジャンルの“再発明”っぽい
正直、「他人の日記」って聞くと、興味ない人もいると思います。
でもこの本は、“ただの日記”じゃない。
日記というより、“思考の試作品集”って感じです。
毎日の何気ない出来事を出発点にして、そこからどこまで思考が広がるか。その「試み」の連続なんですよね。
つまり、「行動の記録」じゃなくて「思考の軌跡」が残ってる。
そしてそれが、読んでる自分自身の思考とも“リンク”してくる。
「ああ、わたしもこんなこと考えたことある」
「でも、ここまで言語化できなかったな」
「いや待てよ、こういう視点もあったのか」
って、読みながらどんどん自分の思考まで引きずり出されるんです。
これ、完全に“日記”の新しい使い方じゃないですか?
④「余白」を読ませる不思議な力がある
この本、明らかに“空白”が多いんです。
すごく饒舌に語ってるようで、実は「何も断言してない」瞬間もいっぱいある。
それが不思議と心地いい。
読者としては、「え、ここで終わるの?」とか「そこは答えないの?」ってなるんだけど、でもその“空白の部分”を自分の中で補完しながら読んでいくのが楽しいんです。
つまり、読みながら“自分の思考”が同時に動き出す。
これは、ただの娯楽本にはない体験だと思います。
⑤ 疲れてる人にこそ読んでほしい
最後にこれだけは言いたいんですが──
この本、めっちゃ“疲れてる日に効きます”。
元気いっぱいで「今日も人生最高!」みたいな日に読むより、
「今日も何もできなかったな……」って落ち込んでるときに読むのがちょうどいい。
むしろそういうときにこそ、「でも、考えてたんだからえらいじゃん」って肯定してくれる感じがあるんです。
生産性ゼロの1日だって、生きてた証なんだなって思わせてくれる。
そんな本、なかなかないですよ。
おわりに
この本は「考えすぎる人」が「考えすぎる自分」をちょっとだけ好きになれる本です。
読んでいるうちに、「こんなふうに世界を見てもいいんだな」「考えること自体が、生きてる証なのかも」って思えてきます。
疲れてる日、なんだか気持ちが空回りしてる日に。
1ページだけでも、読んでみてください。
“ヘラクレスメス”が、きっとあなたの中にも見つかるはずです。
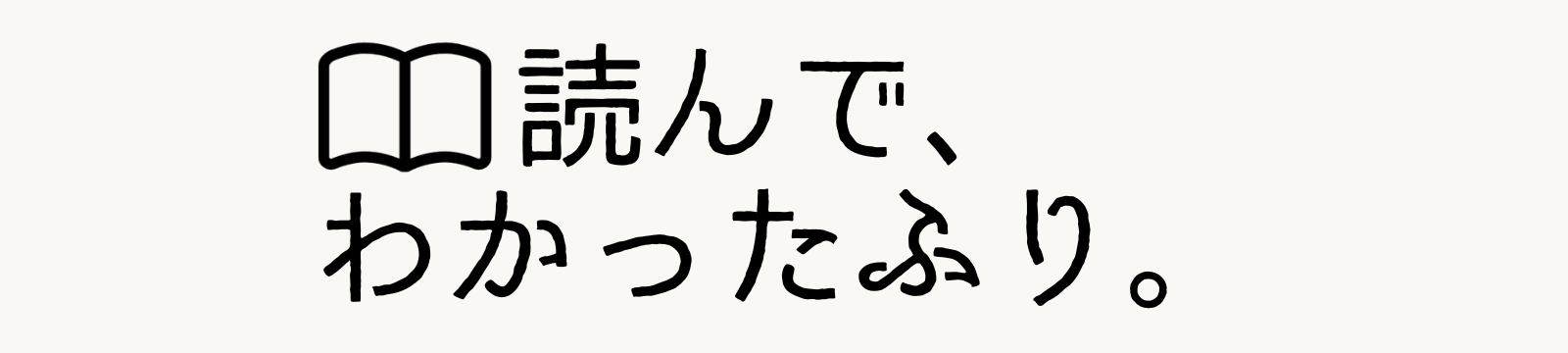
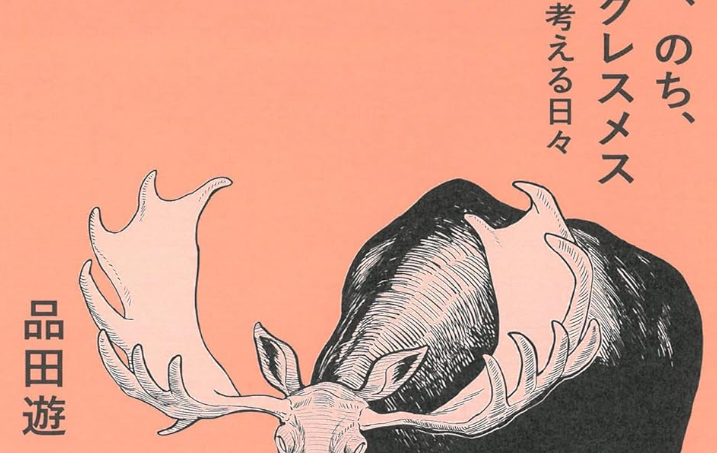

コメント